PENTAXの古いレンズは天体写真に使えるのか実験 ― 2015年12月06日 22時38分10秒
PENTAXのフルサイズデジタル一眼レフカメラの発売が待ち望んでいたのですが、古いフィルムカメラ時代のレンズがどの程度使えるのかということを天体写真としてキチンと比較検証した記事を見かけませんので実験してみました。
今回実験するのはSMC TAKUMAR 50mm F1.4、smc PENTAX-M 50mm F1.4、smc PENTAX-M 50mm F1.7、smc PENTAX-A 50mm F1.7、smc PENTAX-M 24mm F2.8、TAMRON SP 90mm F2.5の6本です。
撮影日:2015年12月5日
撮影場所:富士ヶ嶺
ボディ:PENTAX K-30
ISO 1600、30秒(50mmレンズ共通)
アイベルCD-1と自作モータードライブコントローラによる恒星時追尾
※極軸合わせ不完全で流れている写真あり
■SMC TAKUMAR 50mm F1.4(カビなし、バルサム切れによるクモリなし、黄変あり)
☆絞り開放
☆F2
☆F2.8
■smc PENTAX-M 50mm F1.4(カビなし、バルサム切れによるクモリなし)
☆絞り開放
☆F2
☆F2.8
■smc PENTAX-M 50mm F1.7(カビなし、バルサム切れによるクモリなし)
☆絞り開放
☆F2
☆F2.8
■smc PENTAX-A 50mm F1.7(カビなし、バルサム切れによるクモリなし)
※無限遠ピントずれてる
☆絞り開放
☆F2
☆F2.8
■smc PENTAX-M 24mm F2.8(バルサム切れによるクモリあり)
■TAMRON SP90mm F2.5(カビなし、バルサム切れによるクモリなし)
■所感
50mmF1.4に関してはTAKMARもsmc PENTAX-Mもどちらもほとんど同じ結果に見えるので設計が同じだと言われているのは本当なのでしょう。50mmF1.7については以前にテストした若干のバルサム切れによるクモリありのレンズと今回のクモリなしのレンズのどちらも開放時の輝星の周りのリング状のニジミは同じようにでているのでクモリのせいではなく設計に依存しているのでしょう。
ところが、smc PENTAX-Aの50mmF1.7には輝星の周りのリング状のニジミはないので設計の違いかコーティングの差による違いなのではないかと想像しています。
24mmはAPS-Cにクロップしているにも関わらず周辺の収差が酷いので星撮りには論外でしょう。
TAMRON SP90mmもF4 まで絞ってもフリンジは除去されないのであえて使う必要性は感じません。
50mmはいずれも2.8まで絞ればそこそこ使えるとは思いますので絞り開放だとフリンジとか収差が盛大に出てF値が明るいメリットは構図合わせ程度、ということになってしまいます。
こちらもあえて星撮りにつかうようなレンズではないでしょう。特にF1.4を選ぶ理由はほとんどないと言っていいでしょう。
いずれのレンズもフルサイズのボディが出て使い物になるような性能ではないので、「コレクション」していましたが手放していこうと思います。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://kumikomi.asablo.jp/blog/2015/12/06/7938828/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。





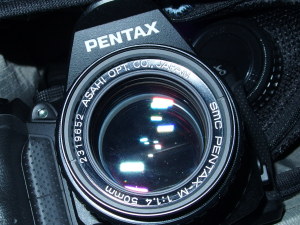


















コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。